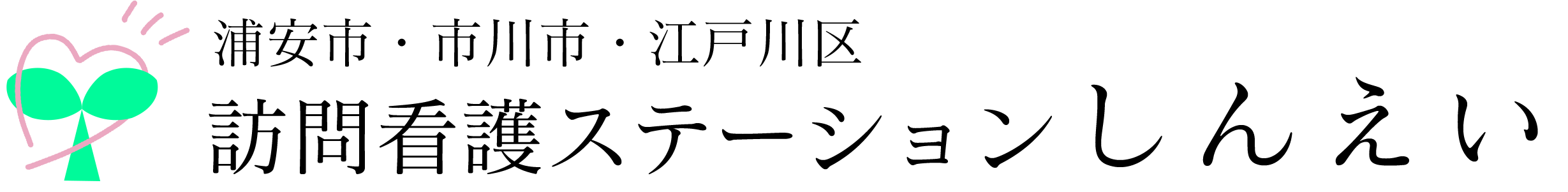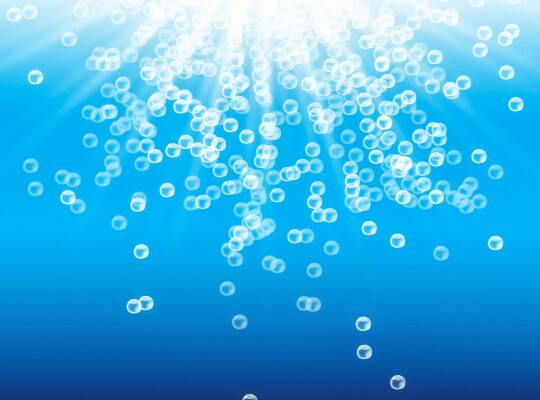2025.03.24
働くこととは
「働かなきゃ…でも不安」そんな声をよく耳にします。
病気やケガ、精神的な不調を経験された方の中には、こんな想いを抱える方が少なくありません。
「またうまく働けるのか不安」
「人とうまく関われる自信がない」
「体調がまた悪くなったらどうしよう」
その“働くことへの不安”は、とても自然な感情です。無理にかき消す必要はありません。大切なのは、その気持ちに自分自身も、周囲も、きちんと向き合うことです。
【不安を抱えながらも「前を向きたい」気持ち】
訪問看護の現場では、そうした不安と向き合いながら、少しずつ生活を立て直そうとする方々と出会います。
大切なのは、“いきなり”働こうとするのではなく、小さな「やってみよう」の積み重ねです。
【「できないこと」より、「今できること」に目を向ける】
私たちは、心の状態や体調、生活背景に合わせて、「その人らしい働き方」を一緒に探します。
今はまだ外で働くのが難しくても、家の中でできることがあるかもしれません。
一日30分だけ、何かに集中してみることも“仕事”の始まりかもしれません。
誰かの「ありがとう」に触れるだけで、心が動き出すこともあります。
訪問看護は、そうした日々の変化を見逃さず、そっと背中を押します。
【訪問看護だからできる、“不安との付き合い方”のサポート】
私たちは、医療・看護の立場からだけでなく、精神的な支え手としても関わります。
・服薬管理や健康チェック
・気持ちの浮き沈みに寄り添う会話
・外出・通所・就労などへの段階的な支援
「働きたいけど不安」──その気持ちがあるからこそ、人は慎重に、丁寧に、前に進めるのだと私たちは思います。
【最後に】
もし、今「働くこと」に不安を感じている方がいたら、ひとりで抱え込まず、ぜひ身近な支援の手を頼ってみてください。
訪問看護は、“こころの再スタート”にも寄り添う存在です。