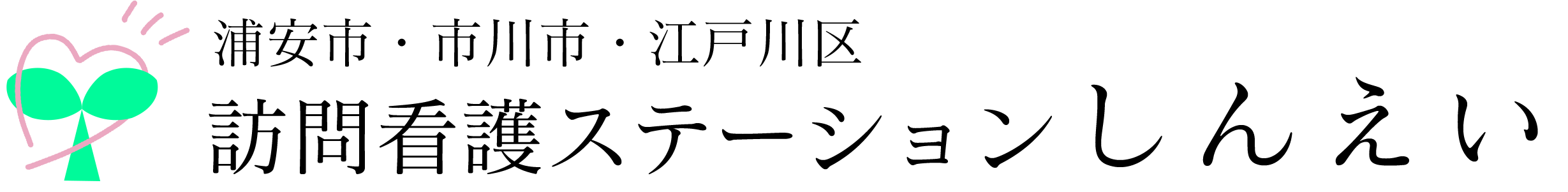2026.02.25
経営方針発表会について
2月21日に伸栄学習会のスタッフが一堂に会し、経営方針発表会を行いました。
青沼塾長からは、「放課後等デイサービスでは今一度原点に立ち返ること」「それ以外の業態である訪問看護やグループホーム、通信制高校、就労継続支援、学習塾、児童発達支援ではコンセプトを明確にすること」のお話がありました。さらに、今弊社は分岐点に立たされているという重要な話がありました。
小泉統括マネージャーからは、2025年度の売上結果と2026年度の数値目標、実行目標、新しい事業についての発表があり、数値が伸びている教室と伸び悩んでいる教室を確認しました。
各業態の発表では、放課後等デイサービスでは、学習支援の質向上に向けた取り組みが共有され、その他の「就労継続支援事業所」「児童発達支援事業所」「訪問看護」「学習塾」「グループホーム」では、コンセプトについて発表がありました。
今回の発表においては、伸栄学習会の「課題」を再確認する時間となりました。まだまだ課題は山積みですが、これを解決していくためにスタッフ一同日々精進していきます。
そして、伸栄学習会は100年・200年続く企業に必ずなります!