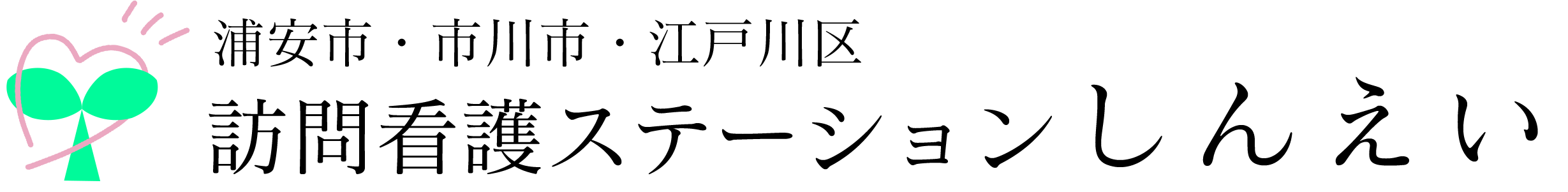2025.03.20
春分の日とは?
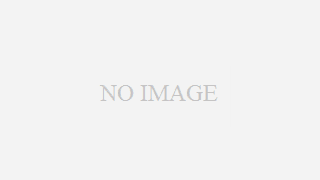 ブログ
ブログこんにちは。訪問看護ステーションしんえいです!
暖かい日が多くなってきましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?道路に花も咲いており、春の訪れを実感しています。
今回は祝日でもある「春分の日」についてお話しします!
春分の日(しゅんぶんのひ)は、日本の国民の祝日のひとつで、毎年3月20日または21日にあたります。この日は昼と夜の長さがほぼ等しくなる日とされ、季節の変わり目を象徴する重要な日です。天文学的には、太陽が春分点を通過する日であり、北半球では本格的な春の到来を告げる日とされています。
春分の日の由来
春分の日の起源は、古くからの自然信仰や農耕文化と深く関わっています。もともと、春分は「祖先を敬い、自然をたたえる日」とされ、日本の伝統的な行事とも結びついてきました。
1. 農耕文化との関わり
古代日本において、農業は生活の基盤でした。春分の時期は、田畑の耕作を始める重要なタイミングであり、豊作を祈る祭りが行われていました。太陽の動きを観察し、暦を決めることは、農作業の計画を立てる上で欠かせないものでした。
2. 「彼岸」の習慣
春分の日は、「お彼岸(ひがん)」とも密接に関連しています。仏教では、春分と秋分の時期に「彼岸」と呼ばれる期間があり、ご先祖様を供養する風習が根付いています。この時期にお墓参りをする習慣は、日本独特の文化として今も広く行われています。
3. 近代の祝日制定
戦前の日本では、春分の日は「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」という祭日で、天皇家の祖先を祀る儀式が行われる日でした。しかし、1948年(昭和23年)に施行された「国民の祝日に関する法律」により、「春分の日」として新たに制定され、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と定義されました。
春分の日に行われる行事
1. お彼岸のお墓参り
春分の日を含む1週間(前後3日間+当日)は「春のお彼岸」と呼ばれ、ご先祖様のお墓参りをする家庭が多いです。また、おはぎ(ぼたもち)を食べる習慣もあります。
2. 春の訪れを祝う行事
全国各地で春の訪れを祝う祭りが行われ、農作業の開始を告げる神事や、桜の開花を楽しむ行事もあります。
3. 自然や動植物を大切にする日
春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として制定されたことから、環境保護活動や植物を植えるイベントなども開催されます。
まとめ
春分の日は、ご先祖様を敬い、自然や動植物に感謝の気持ちを伝える・持つ意味合いがあると感じました。
ご先祖様や自然・動植物に感謝の気持ちを持ちつつ、皆様にとって素敵な祝日となることを祈っております。
ご覧いただきありがとうございました!