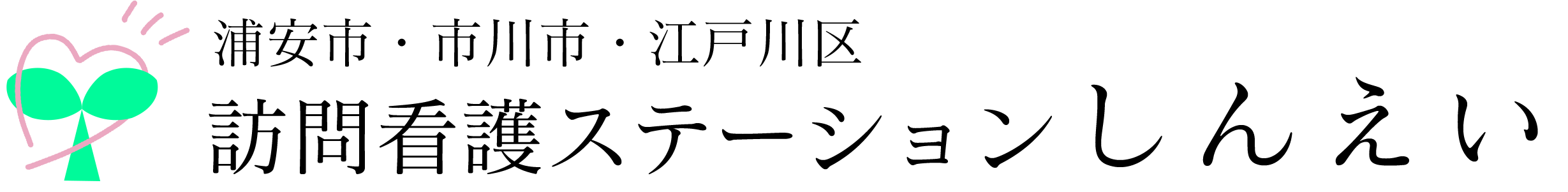2026.02.28
「🌸 3月 ― それぞれの“次の一歩”へ 🌸」
こんにちは!訪問看護ステーションしんえいです
少しずつ寒さがやわらぎ、
日差しの中に春を感じるようになりました。
3月は、別れと始まりが重なる特別な季節です。
卒業、進級、そして新たな環境への変化。
嬉しさと同時に、不安を感じやすい時期でもあります。
🌷 不安が強くなる季節
「4月が不安です」
「環境が変わるのが怖い」
「ちゃんとやっていけるか心配」
春は前向きなイメージが強い一方で、
“変化”が苦手な方にとっては大きな負担が伴うこともあります。
新しい学年、新しい進路、新しい生活が始まるとき、
不安を抱えるのはごく自然なことです。
🌷 できていることを確認する
毎日学校に行けている。
部屋から出られるようになった。
ちょっとした会話ができた。
どれも小さなことのように見えて、実はとても大きな前進です。
🌷 春は“準備の季節”
春は、いきなり大きな変化を求める季節ではありません。
むしろ、「準備」の時期です。
無理に大きな一歩を踏み出す必要はありません。
小さなことを積み重ねるだけで、
大きな変化に繋がります。
私たちの訪問看護は、心のケアを中心にサポートを行っています。
私たちは“小さな成功”をしっかりと確認し、この季節に向けて次のステップへ繋がる支援を行い、ご利用者様と共に“次の一歩”を支えていきます。